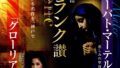15時開演 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール
PAC定期は大体いつも半日年休を取って1日目の金曜日に行くのですが、今回はこの前日に業務がひと区切りついたこともあり、ちょっとしたご褒美気分で行ってきました。

伊福部昭、ラフマニノフ、バルトーク、という「民族色が滲む」ラインナップのプログラム。
1曲目は「ゴジラ」の映画音楽で知られる伊福部昭の舞踊音楽「サロメ」から「7つのヴェールの踊り」。「7つのヴェール」というとまず浮かぶのは、R.シュトラウスのオペラ「サロメ」ですが、こちらは日本のバレエ団からの委嘱作品。「民族色」といっても、これは「日本」ではなく「アイヌ」。
冒頭の低音フルートの深い音色のソロ、弦楽器の幻想的な響きは、西洋でもなく東洋でもない不思議な浮遊感。なんともいえない魅力を感じましたが、やがて打楽器がリズムを刻み始めたところから、もうこれは「ゴジラ」でしかないでしょう、と(笑)。今も脳内再生されているのはゴジラのテーマです。でも、このリズミックな音楽、かなり好きです。最後列でしかも隣席は両側ともガラ空きだったので、心置きなく体でリズムを取って聴きました。
曲のラスト、マエストロが一瞬かがんで「よいしょ」といったゼスチャーをすると、奏者全員が一斉に立ちあがって「ジャーン!」。これには思わず「ほー!」と歓声を上げてしまいました。若い指揮者と若者のオケならでは、そしてサービス精神旺盛かつホーム感満載のここ芸文センターならではのパフォーマンスです。PAC定期、やはり毎回楽しませてくれます。
カーチュン・ウォン氏の指揮は、大フィル、センチュリー、そしてこのPACでも以前に観ていますが、受ける印象はいつも同じで、「あぁ、アジアのオーケストラだなぁ」。日本人の指揮者ではそうは感じないのですが、中華系っぽい(と思ってしまう)独特の動きのせいでしょうか。しかしその指揮動作は、後ろから見ていてもとても分かりやすく、右手左手を同時に全く別々の用途に使っていたりして、なんとも器用だなぁ、と感嘆してしまいます。
コンチェルト以外の編成は弦16型。コントラバスだけが離れて正面後ろに並ぶ、ちょっと変わった配置で、ダイレクトに低音が響いてくるのが効果的でした。
2曲目は、楽しみにしていた三浦謙司さんの独奏でラフマニノフのピアノ協奏曲第3番。
三浦さんは、昨年5月にここの小ホールでリサイタルを聴き、次はコンチェルトを聴きたい、と思っていたところ、意外と早くにその願望が叶いました。しかも私の「ど真ん中」のラフマニノフ(笑)。
——とさて、この3番は今年の6月、務川慧悟さんで聴いて、ちょっとないくらい感動したのですが——その感動があまりにも大き過ぎたせいでしょうか、残念ながら、少々物足りなさを感じてしまいました。
冒頭あの有名な一節が響き始めたときに、あ、これはちょっと・・と思ってしまったのが、音量。小さめであまり響いてこない。これは多分途中で化けることはないパターンかと思いつつ、期待しながら聴いてはいましたが、とうとう最後まで掴まれるものがないままに終わってしまいました。
前の感動が大きくても、次にまた違った感動を得られるだろうとの期待で足を運んだのですが、少々残念。3年前のロン・ティボー・クレスパン国際コンクールでは、1位が三浦さん、2位が務川さん。コンクールの順位というのは時の運でもあるのだなぁ、とも感じてしまいました。
けれど、アンコールのケンプ編ヘンデルのメヌエットの潤いのある弱音が非常に美しかったことと、ユーモアとあたたかさを感じる三浦さんの佇まいがなんだか好きで、またリサイタルがあれば行きたいと思っています。
後半は、バルトーク「管弦楽のための協奏曲」。
——初めに書きましたが、この週は気の張る仕事でこの日は腑抜けモードだったこともあり、クラオタ・アンテナをしゅるしゅるっと格納し、意識朦朧で聴いておりました。すみません。
◇ソリスト・アンコール ヘンデル/ケンプ編「メヌエット ト短調」
◇オーケストラ・アンコール 外山雄三「管弦楽のためのラプソディ」より「八木節」
このアンコール冒頭の拍子木でばちっと目が覚めました。この頭打ちのリズム、日本人のDNAが騒ぎますね(笑)
◇座席
2階下手側最後列。後ろの方はかなり空いていて視界良好。同じ列では端と端に客がいるだけで、観客としてはかなり快適。