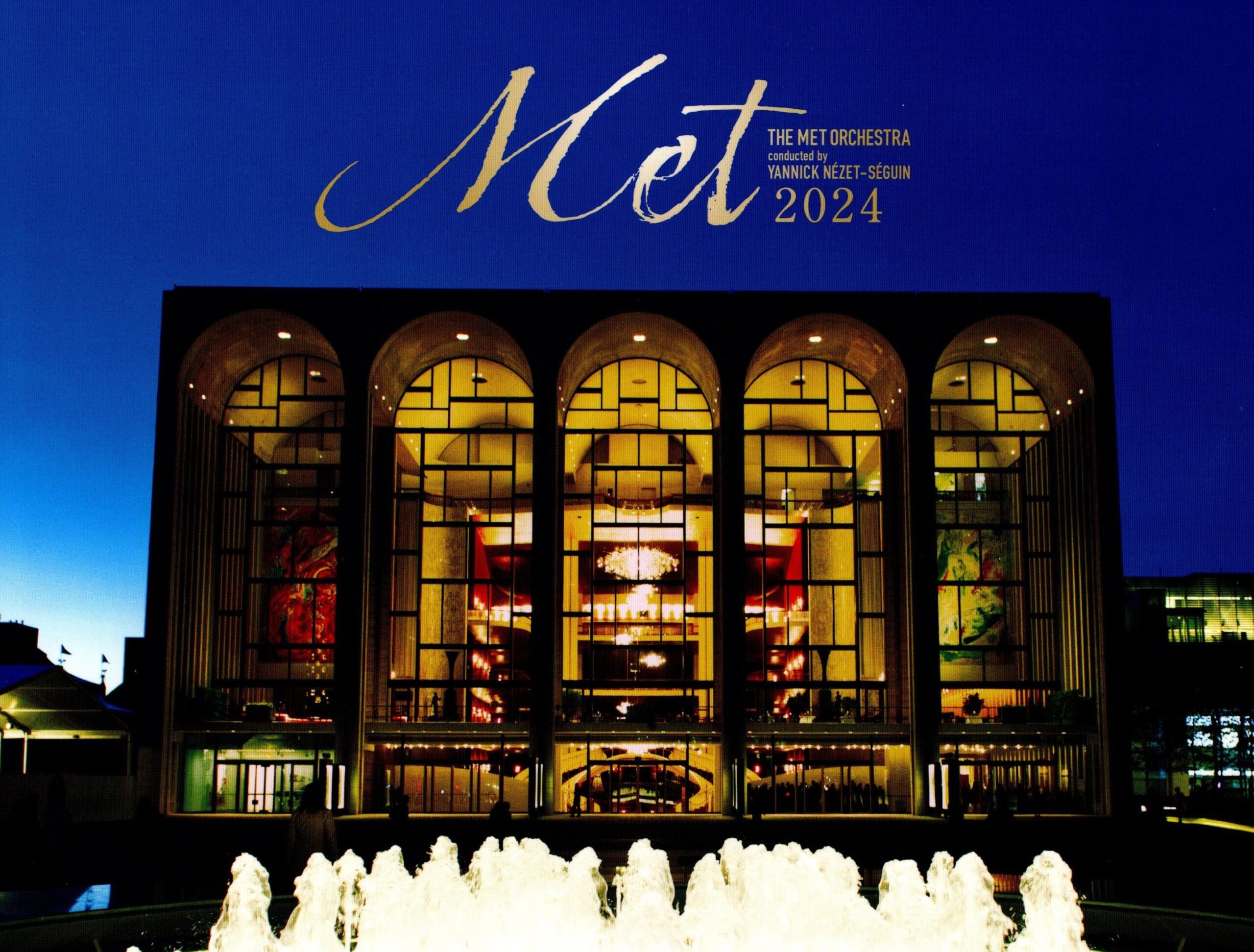15時開演 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホール
ライブビューイングでお馴染み、いつも映画館で聴かせていただいているMETオケ。
ようやく生で鑑賞できました。


スクリーン越しに拝見しているマエストロ ネゼ=セガン氏やエリーナ・ガランチャ氏がNYに行かずとも生で鑑賞できるまたとないチャンス。ちょうど2年前の来日公演が中止になったときは残念でしたが、その間に我がネゼ=セガン愛も深まったところでの待望の来日でした。
前半はオケのみで、ワーグナー「さまよえるオランダ人」序曲とラインスドルフ編曲によるドビュッシー「ペレアスとメリザンド」組曲。後半は演奏会形式でバルトーク「青ひげ公の城」。謎めいた登場人物、不気味かつ不可思議な物語という共通点があります。
オーケストラは(意外にも)対向配置。弦16型で後半は4管の大編成。正面の木管の後ろがホルン、上手側の区切られたひな壇にトランペットとトロンボーンおよびテューバが並び、その後ろにティンパニという配置。こうするとコントラバスとテューバ・トロンボーンが左右に分かれ、低音のステレオ効果があるのですね。見た目に整然としており、合理的だと感じました。
オーケストラ全体の響きは柔らかなまとまりがあって美しい。ダイナミック・レンジの幅が広く、緩急もしなやかで機動性を感じました。物語に寄り添う演奏をしているオーケストラ、という印象。もちろんこれはマエストロの手腕によるところも大きいと思います。
「ペレアスとメリザンド」の浮遊感ある音楽にはただうっとりと浸るばかり。輪郭のはっきりとした響きなのですが、前述のフレキシビリティを感じる演奏で、特に消え入る様に終わっていった曲の結びは息を呑む美しさ。デクレッシェンドがこんなに美しいとは。オペラの演奏で歌手に合わせて音量を絞る、それも滑らかに、ということにやはり普段から慣れているのかと思った次第です。
後半「青ひげ公の城」。
この作品を持って来てくれたことに感謝。素晴らしかった。
ライブビューイングでもおなじみの現代屈指のメゾソプラノ、エリーナ・ガランチャ氏。バスのクリスチャン・ヴァン・ホーン氏は上背もあり堂々の立ち姿。そこにいるだけで説得力。ちなみにプロフィール写真よりかっこよかったです。
吟遊詩人によるプロローグは、PAを使ったナレーションで行われました。その間にそれぞれ左右の扉から歌手が登場。二人が歌い始めた瞬間、その深い発声と声量に感嘆。後ろのオケが大音量で鳴っていても、まったく遜色なく響くのです。特に第五の扉が開かれる全曲頂点の箇所、オケの音量にも驚きましたが、それを凌駕するガランチャ氏の声量には驚愕。凄すぎる‥。
このオペラ、サスペンス・ホラーなあらすじといい、バルトークの「夜の音楽」といい、全体に漂うダークでありながら透明な雰囲気が以前から好きだったのですが、オーケストラを眺めながら聴くとわかることが多く、非常に聴きどころの多い音楽なのだと再認識しました。演奏会形式で聴けてよかった。舞台装置がない分、意識をそちらに取られることがなく、音楽に集中できるのです。
この作品は現代音楽に近いものがあり、いわゆる劇伴音楽のような箇所や、楽器で効果音を鳴らす箇所(金管楽器の空吹きによる風切り音など)もあったりするので、想像力を働かせながら(職業柄、城の間取りを考えたりもしつつ)聴くのは楽しい時間でした。
しかし、一度で捉え切るには我が脳ミソの容量が足りず、もう一度、いや何度でも聴きたい、そんな思いも抱いた鑑賞体験でした。
マエストロが手を完全に下ろしてから、やや長めの静寂を破ったのは、1階前方の「ブラボー」でした。
◇アンコール
なし。
拍手を制したマエストロ。日本語で「アリガトウゴザイマス」のあと、「この後なにかを演奏するのは難しい。明日また来てください」というようなこと(たぶん)を仰って笑いを取り、スタオベの中去って行かれました。
◇座席
3階席上手側最後列。
4階席ががっつり被さるなかなかの天井桟敷感。2階席最前列を取ったような気がしていたけれど、それは2年前の記憶でした‥。
1階席後方は見えなかったけれど、客入りは7~8割程度? 前の2列がガラ空きだったので視界は良好。が、もっと前の席で臨場感を味わいたかったな、と。
ホワイエにサイン入りポスター